
近年、話題になっている「ダイバーシティ」。
ダイバーシティ経営や、ダイバーシティマネジメントなど、多くの企業や組織がダイバーシティを推進しています。
実は、ダイバーシティは、企業だけではなく、子どもや教育とも関係があるのです。
今回は、ダイバーシティとは何か、子どもとダイバーシティについて解説し、子ども向けのダイバーシティのおすすめの絵本をご紹介します。是非、参考にしてみてください。
目次
ダイバーシティとは何か
ダイバーシティ(divercity)とは、
「多様性」
という意味を表す言葉で、様々な背景をもつ人たちが集まる状態を指し、人種、性別、年齢、障害の有無、宗教、価値観、趣味嗜好、職歴などの違いを認め合い、尊重し合うということです。
今、様々な場面で使われているダイバーシティ。
組織・企業では、人種・年齢などにこだわらず、多様な人材を生かして最大限の力を発揮する、という考え方で用いられます。
学校現場では、一人ひとりの子どもの個性、多様性を受け入れ、お互いを尊重し合うという考えのもと、「ダイバーシティ教育」を取り入れています。
文化や言語、性の悩み、片親家庭、障がいなどの悩みを抱える子どもに配慮する教育が、「ダイバーシティ教育」です。
以上のことから、ダイバーシティは「多様性」という意味で、教育の中でも、現在非常に重要視されている言葉だと分かります。
子どもとダイバーシティについて―差別との関係―
「ダイバーシティ」は、もともとアメリカで、社会的マイノリティや女性などの差別や偏見に取り組む動きの中で広まった言葉。
そして差別は、大人だけではなく子どもたちの中にも起こりうることです。
例えば、日本の学校現場では、外国から来た子ども、障がいをもつ子ども、経済的に余裕のない子どもなどに対する偏見や差別によるいじめが問題視されています。
子どもと差別について、心理学では有名な『泥棒の洞窟』実験があります。
社会心理学者のシェリフら(Sherif et al., 1961)は、「泥棒洞窟州立公園」のサマーキャンプに参加出来る少年たちを集めました。
参加した少年たちを2グループに分け、それぞれで集団生活を開始。
グループは1週間で、グループ名や役割分担を決め、おそろいのTシャツを作るなど、結束力を高めていました。
そこでシェリフらがキャンプ設備は2グループ共同で使用するようにと告げると、今まで穏やかだった少年たちが他方のグループに競争心をむき出しにし、相手のグループ旗を燃やすなど、敵対行為に出てしまいました。
この出来事は、「内集団バイアス(内集団びいき)」という心理現象が関わっています。
「内集団バイアス」とは、自分が所属する集団(=内集団)に対し高く評価し、好意的な態度をとること。一方で、自分が所属する以外の集団(=外集団)を低く位置づけ、敵対し、差別や偏見が生じる源となる。
この「内集団バイアス」は、自分や自分が所属している集団と少しでも違う人や集団と出会うことで、誰にでも起こりうる心理状態なのです。
子どもの人種差別教育について、子育ての本『間違いだらけの子育て』(ポー・プロンソン著)によると、異文化・異人種で交流を増やしても差別はなくならず、周囲の大人がしっかりと説明しなければ、子どもは学習できないと言われています。
以上のことから、少しの違いで差別・偏見は子どもでも生じる可能性があること、差別の解消につなげるためにも、子どもが「多様性」について大人としっかり学ぶ必要があることが分かりますね。
「ダイバーシティ」絵本を読むメリット
子どもがダイバーシティを学ぶ方法として、絵本を読むことをおすすめします。
以下では、「ダイバーシティ」絵本を読むメリットを3点挙げています。
メリット①:幅広い知識が身に着く
「ダイバーシティ」絵本を通して、子どもであっても、社会でどのようなこと問題が起きているのか、何を知る必要があるのかを知ることが出来ます。
それも難しい言葉ではなく、わかりやすい言葉、やさしい話で社会における幅広い知識が身に着く。
読みながら、大人がさらに知識を補足することで、子どもの理解がより深まります。
メリット②:多様な視点で物事を考えることができる
ダイバーシティや多様性を学ぶことで、自分が考えていることが必ずしも正解であると考えず、様々な角度から物事を考えることができるようになります。
絵本を通して、この絵本の登場人物はこういう考えだった、絵本でこういう話があったなど、“視点を変えてみる”という習慣が身に着くことも。
また、“視点を変えてみる”ことは、物事を深く考えるだけではなく、物事や他人に対して寛容にもなれます。物事や他人に対して少し違和感を感じても、その背景を考えることで受け入れやすくなり、自分自身も楽になります。
メリット③:自分を知り、受け入れる
多様な視点が身に着くということは、自分への理解も深まるということです。
絵本を通して、自分がどのような家庭のもとで生まれ、どのような価値観や文化を持っているのかが分かるようになります。
さらに、絵本を読む中で、「この登場人物は今の自分と似ている」と感じることもあるでしょう。自分と似ている人がいると「自分はこのままでいいのだ」と安心して自分を受け入れることができますね。
「ダイバーシティ」絵本のおすすめ5選
以下では、おすすめの「ダイバシティ」についての絵本を5冊ご紹介します。
是非、参考にしてみてください。
家族の形を考える絵本:いろいろいろんなかぞくのほん/メアリ・ホフマン
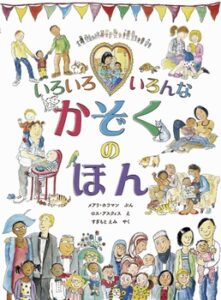
えほん | いろいろ いろんな からだの ほん | 少年写真新聞社のホームページ (schoolpress.co.jp)
年長や小学校低学年以上から読める絵本。
世界のいろいろな家族について解説しています。
一人親家庭、おじいちゃんおばあちゃんと住んでいる家庭、LGBTの家族、休日の過ごし方、通っている学校、働いている場所など家族によって違いがある。
家族の形、ライフスタイルが多様化している今だからこそ、読んでほしい一冊です。
家族の多様性を学べると同時に、自分の家族はどんな家族なのか、自分への理解も深まります。
ジェンダーを考える絵本:ピンクがすきってきめないで/ナタリーオンス
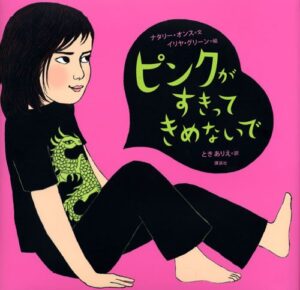
『ピンクがすきってきめないで』(ナタリー・オンス,イリヤ・グリーン,とき ありえ)|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)
3歳から読める絵本です。
女の子は、ピンクが好きじゃなきゃ、だめなの?
“わたし”は黒が好きな女の子。
まわりからは女の子らしくしなさいって言われるけど、女の子らしくとはどういうこと?
多くの人が性別についての固定観念をもっています。
しかし、果たしてそれは正しいのでしょうか?
そんな疑問を読者に投げかける、大人が読んでもはっとさせられる絵本です。
女の子らしく、男の子らしくしないといけないなど、性別の固定観念によって息苦しさを感じる子どもに、この絵本は優しく寄り添ってくれます。
障がいを考える絵本:みえるとかみえないとか/ヨシタケシンスケ
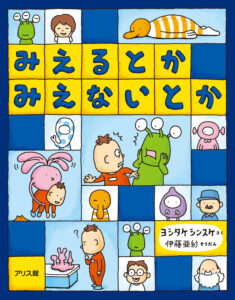
みえるとか みえないとか – 本をさがす – アリス館 (alicekan.com)
宇宙飛行士のぼくがとある星に降り立った。
その星に住んでいるものたちは、なんと目が3つある!
ここの星の人たちは、目が2つしかないぼくのことを「かわいそう」という。
そこで、ぼくは目の見えない人に話しかけることにした。
ユーモアたっぷり、ヨシタケシンスケの作品。
宇宙人という子どもたちが興味を引くような話を通して、目が見えること、目が見えないこととはどういうことかを分かりやすく解説。
視覚障がいを知るきっかけ、深く考えるきっかけになります。
障がいを考える絵本:すずちゃんののうみそ 自閉症スペクトラム(ASD)のすずちゃんの、ママからの手紙/竹山美奈子
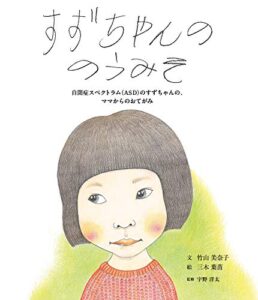
すずちゃんののうみそ – 株式会社岩崎書店 このサイトは、子どもの本の岩崎書店のサイトです。 (iwasakishoten.co.jp)
自閉症スペクトラムのすずちゃんの話。
すずちゃんは、年長になってもくつを一人で履けず、おしゃべりもできません。
そんなすずちゃんに疑問をもった保育園のお友だちに、すずちゃんのママは手紙で答えました。
優しい物語を通して、子どもや大人に自閉症スペクトラムについて解説。
難しいテーマを扱っていますが、とても分かりやすい内容になっています。
巻末には、自閉症スペクトラムの特徴紹介、医学監修の先生からのメッセージも。
自閉症スペクトラムなど発達障がいについて知りたいときに、おすすめの一冊。
人種を考える絵本:せかいのひとびと/ピーター・スピア

せかいのひとびと (児童図書館・絵本の部屋) | ピーター・スピアー, 松川 真弓 |本 | 通販 | Amazon
地球にどのような人が住んでいるのか、どのような暮らしをしているのか、世界にいるたくさんの人々を紹介している絵本です。
体の大きさ、肌の色、暮らしている家、話している言葉などなど、分かりやすく絵や文章にして教えてくれます。
「世界にはこんなにたくさんのひとたちがいるんだ!」
世界をまだよく知らない幼いこどもでも、絵本に夢中!
読みながら、大人からも、文化や人種についてさらにわかりやすく解説すると、より知識が広がります。
「ダイバーシティ」絵本の選び方
選び方①:関心のあるジャンルから選ぶ
ダイバーシティの絵本は、障がい、宗教、民族、家族など様々なジャンルを扱っています。
どのジャンルがいいのか迷った際には、子どもが今一番関心のあるもの、身近に感じるものを選びましょう。
また、1つのジャンルであっても、違う視点に立った絵本を複数選ぶのもおすすめ。
例えば、「発達障がい」の絵本を選んだとしても、当事者の視点で描かれた絵本と、周囲の視点で描かれた絵本とでは全然違いますので、異なる視点に立った絵本を選ぶといいですね。
選び方②:分かりやすい文章のある絵本を選ぶ
分かりやすく、シンプルな文章で書かれた絵本を選びましょう。
難しいテーマを扱っているため、子どもにも優しく、わかりやすく説明してくれる絵本がいいですね。
年齢や発達段階に合わせて、文章を選ぶのもポイントです。
選び方③:目を引くイラストのある絵本を選ぶ
難しいテーマであるため、どうしても絵本に興味が湧かない子どももいますよね。
その場合は、子どもが好きそうで、インパクトのあるイラストで描かれた絵本を選びましょう。幼い子供にとって、文章や内容よりも、絵本の中で一番目立つイラストの方に目が行きやすいです。
食べ物、動物、乗り物など子どもの好きなものが登場する絵本もおすすめです。
大切なテーマではありますが、あくまで子どもの気持ちを優先し、無理のない範囲で絵本をすすめてみましょう。
まとめ
今回は、ダイバーシティの定義や子どもとの関係について解説し、その上で「ダイバーシティ」絵本を読むメリットとおすすめの絵本をご紹介しました。
子どもたちは、絵本を通して価値観や文化を学びます。
是非、絵本をきっかけにたくさんの価値観や文化に触れ、ダイバーシティや多様性について一緒に考えてみてください。
(参考図書)武藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治著「心理学」株式会社有斐閣出版
ポー・プロンソン著「間違いだらけの子育て」インターシフト出版







返信