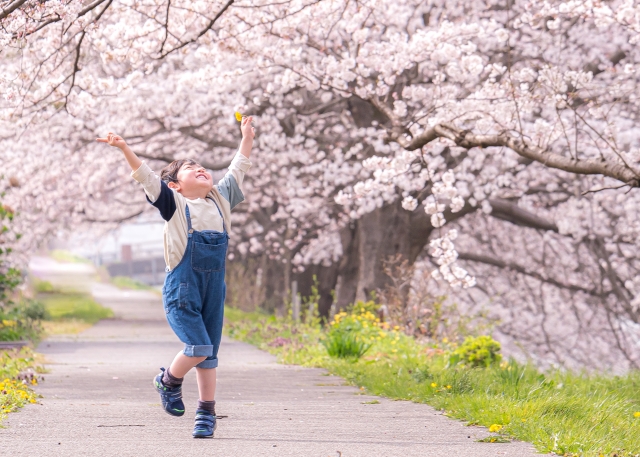
支援センターは何ヶ月から行くのが良い?ママ友の作り方も紹介!
赤ちゃんと2人で家にずっといると、ママも気持ちが滅入ってしまうこともあります。
そのようなときに支援センターに行って、気持ちをリフレッシュする人が多いです。
しかし生後何ヶ月頃から支援センターに行き始めるのが良いのか、何を持っていけばいいのか疑問に思う人がいます。
またママ同士の輪に入れるのか、どうしたらママ友が出来るのか不安に思う人もいます。
この記事を最後まで読むと、このような疑問や不安を解消できます。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
支援センターは何ヶ月から行きはじめる?

支援センター自体は生後0ヶ月から利用できます。
生後0ヶ月から首が座る頃の赤ちゃんを支援センターに連れて行っても意味があるのかと思われがちですが、この時期はママのリフレッシュが一番の目的と考えると意味があるものになります。
赤ちゃんと1日中2人きりでいる日が続くと、ママは悶々とした気持ちになってきます。
そのため、ママのリフレッシュを目的にして行ってみてください。
また首が座る頃には寝返りも出来るようになってくるので、赤ちゃんは自ら興味があるところへ移動して、おもちゃで遊べます。
支援センターに行きはじめる1番多い月齢は生後6ヶ月以降です。
生後6ヶ月くらいになると、支援センターで開催されるイベントにも楽しく参加できるようになってきます。
赤ちゃんの意思がしっかりとしてきて移動も自分で出来るため、家にずっと2人でいるとママも疲れてきてしまいます。
支援センターにはいろいろなおもちゃがあるので、自分が興味を持ったおもちゃのところへ移動して、楽しめます。
支援センターに持っていくもの

おむつ、おしりふき、使用済みおむつを入れる袋
場所によってはおむつを捨てる場所がなく、持ち帰ることになるかもしれません。
事前に確認して、もしおむつ用のゴミ箱がなければ、袋を持参してください。
飲み物
支援センター内は過ごしやすい温度管理が徹底されています。
しかし赤ちゃんはたくさん動くので、すぐにのどが渇いてしまいます。
そのため、お茶など普段水分補給として飲んでいるものを持って行ってください。
また、まだミルクを飲んでいる場合はお湯と湯冷ましを持っていきましょう。
場所によってはお湯が用意されているところもあるため、事前に確認をしておくと荷物を減らせるかもしれません。
着替え
おむつから漏れてしまったり、飲み物をこぼしてしまったとき用で、1組くらいは着替えを持っていくと安心です。
支援センターに行く時間帯
一番混んでいる時間帯は開館からお昼前です。
家事を終わらせてから支援センターに行き、たくさん遊んだ後にお昼寝をしてもらおうと考えている人が多いです。
この時間帯は混んでいますが、幼稚園に通っている子の利用はないため、小さい子がたくさん利用しています。
一番空いてる時間帯はお昼頃から14時頃です。
お昼前に帰宅する人が多いため、一番空いています。
落ち着いた中で遊ばせたいと考えているのであれば、この時間帯の利用がおすすめです。
14時以降は幼稚園終わりの子の利用が増えてきます。
少し大きい子が走り回ったりするので、自分の子供の月齢次第では危険に感じてしまうこともあります。
しかしお兄ちゃんお姉ちゃんと関わることで、普段とは違う刺激をもらえるというメリットも考えられます。
支援センターに行くメリット・デメリット
支援センターに行くことによるメリットやデメリットを紹介していきます。
支援センターに興味はあるけど、あと一歩が踏み出せないという人はぜひ参考にしてみてください。
支援センターに行くメリット
支援センターに行くことでママにも赤ちゃんにも良いことはたくさんあります。
その中でも特にメリットに感じることを紹介していきます。
育児の情報交換が出来る
日中1人で育児をしていると、育児に関して不安に思うことや悩みがたくさん出てきます。
他のママと話すだけでも気が楽になりますし、もし良い情報を知っていたら解決方法を教えてくれることもあります。
自宅にないおもちゃで遊べる
家で遊んでいるおもちゃばかりでは赤ちゃんも飽きてしまいます。
しかしおもちゃをどんどん買い足していくと、家の中がおもちゃで溢れてしまいます。
支援センターに行くと家にはないおもちゃで遊ぶこともできますし、滑り台やボールプールなど体を思い切り使える遊具もあるので、赤ちゃんも喜んでくれます。
息抜きができる
支援センターに行くと同じ状況のママと話せるので、「大変なのは自分だけじゃない」と再認識ができます。
また普段は赤ちゃんと2人きりで、話し相手が赤ちゃんしかいませんが、支援センターでは大人と会話ができるのでストレス発散になります。
支援センターに行くデメリット
支援センターに行くことのデメリットを紹介していきます。
メリットよりデメリットのほうが大きく感じてしまう人もいるので、支援センターに行く前にデメリットも理解しておきましょう。
風邪をもらう可能性がある
他の子のママの考え方によっては「少しくらい鼻水が出ていても大丈夫だろう」と、鼻水が出ている子を支援センターに連れてくるということもあります。
特に低月齢の赤ちゃんはおもちゃを口に入れて舐めたりもするので、風邪など感染症をもらう可能性が高くなります。
ママ同士のコミュニケーションに疲れてしまう
ママ友が出来て情報交換ができるというメリットがありますが、人によってはそのコミュニケーションで疲れてしまうこともあります。
支援センターでは子供同士のおもちゃの取り合いなどをママ同士が間に入って譲り合ったりしますが、そこも気疲れしてしまう部分です。
知っている人が多いと疲れてしまうので、たまには別の支援センターを利用して、周りとあまり関わらずに過ごすのも一つの手段です。
他の子と比べてしまう
同じくらいの月齢の子を見て「うちの子はまだハイハイが出来ないのに、あの子は出来ている」などと比べてしまうことがあります。
赤ちゃんの成長は人それぞれだと分かっていても、気になってしまうものです。
赤ちゃんのことは支援センターのスタッフに相談することも出来るので、気になってしまう人は相談をしてみましょう。
支援センターでのママ友の作り方

支援センターならではのママ友の作り方について紹介していきます。
ママ友がいると情報交換なども出来るようになるので、ママ友の存在は心強いです。
ぜひ参考にしてみてください。
まずはあいさつから
近くにいるママにとりあえずあいさつをしてみましょう。
相手から話しかけてくれるのを待っているだけでは、ママ友はなかなか作れません。
また自分から声をかけたほうが「話しやすそう」「人当たりがいい人なのかな」などという印象をもってくれます。
自分がどのような雰囲気の人なのかを知ってもらうためにも、自分から声をかけてみましょう。
歳が近そうなママに声をかける
近所の支援センターで歳が近い人ということは、自分や夫が通っていた学校が一緒だったり、共通の知り合いがいるかもしれません。
育児以外の話題も出来ると、相手との距離感がぐっと縮まります。
子供同士で遊んでいるママに声をかける
子供同士が一緒に遊んでいるということは、子供の月齢が近いことが多いです。
月齢が近い子のママとは不安に思っていることなども似てくるので、お互いが共感しやすい話題も多く、会話に困らなくなります。
子供の成長のことや、離乳食の話なども出来ると会話が広がり仲良くなれる可能性が高くなります。
保活の話題をしてみる
近所の支援センターだと保活についての相談や共感が出来る可能性が高いです。
月齢が近い子のママとは、保活に対しての不安に共感できますし、月齢が上の子のママだと保活の相談に乗ってくれます。
同じ保育園に入園することになれば、入園後も困ったときなどにすぐ相談し合えるママ友になるかもしれません。
あまり考えすぎないようにする
「絶対にママ友を作る」と思っていると空回りをしてしまったり、もしその日にママ友が出来なかった場合、とても悲しい気持ちになります。
ママ友のことはあまり考えすぎずに、子供が楽しく遊べたらいいなくらいの気持ちで支援センターに行ってみましょう。
その方が肩の力が抜けて、意外と周りから話しかけてくれたり、自分からも自然と声をかけやすくなります。
まずは一度支援センターに行ってみましょう
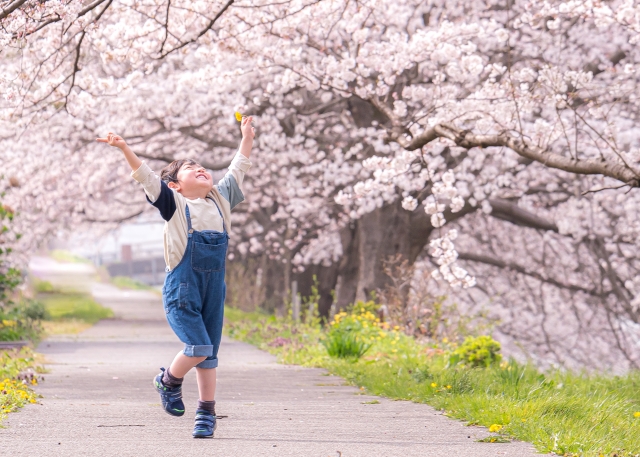
低月齢用のイベントもあるので、イベントだけに参加してみても良いです。
自分が思っている以上に楽しめるかもしれません。
最初はママ友のことは考えすぎずに、雰囲気の確認や顔を出すだけという気持ちで利用してみましょう。
子供だけではなくママのリフレッシュもできる場所になるかもしれません。







返信